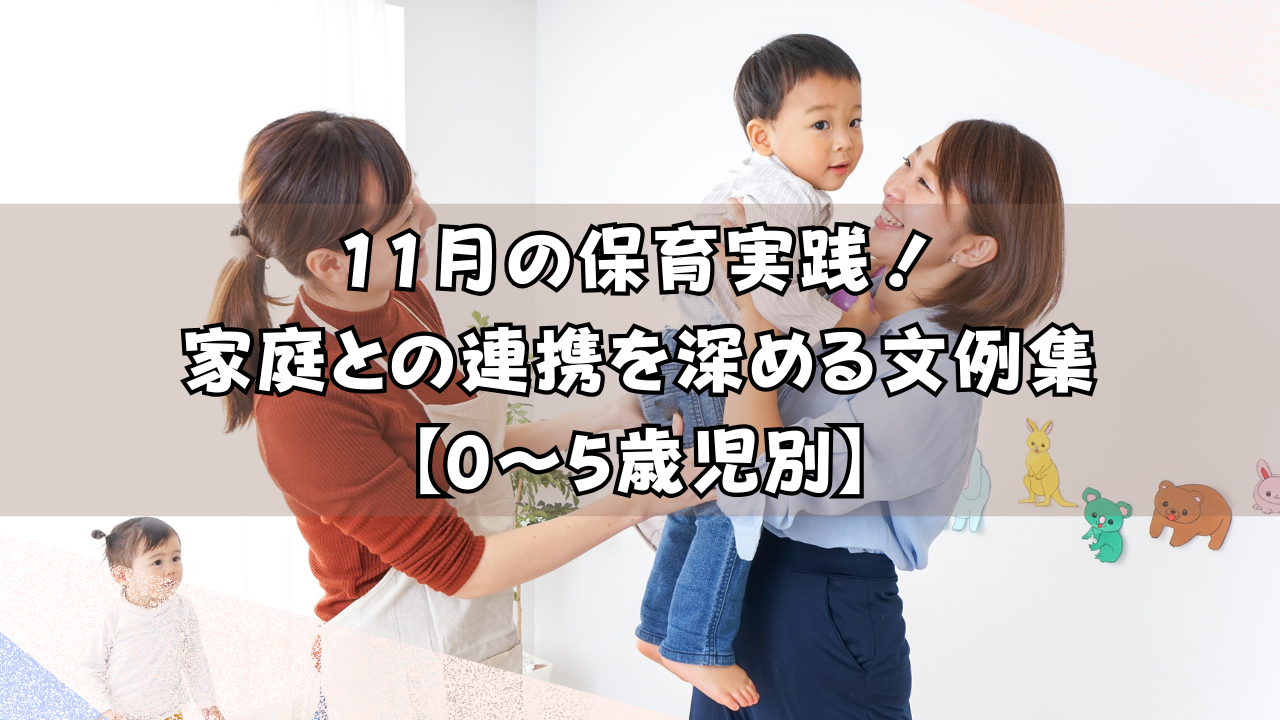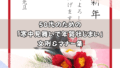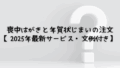11月は寒さが本格化し、感染症や体調の変化が気になる季節です。
同時に収穫祭や作品展など行事も多く、園と家庭が力を合わせて子どもを支えることが一層大切になります。
この記事では、0歳から5歳児クラスまでの年齢別に「11月の家庭との連携に役立つ例文」をまとめました。
連絡帳や保育通信にそのまま使える文例を多数掲載しているので、「どう書いたら伝わりやすいかな?」と迷ったときの参考にしていただけます。
健康管理・生活習慣・行事の協力依頼など、家庭と一緒に取り組める声かけのヒントが詰まっています。
園と家庭が同じ方向を向いて連携することで、子どもたちが安心して成長できる11月を一緒に作っていきましょう。
11月の保育における家庭との連携のポイント
11月は気温が一気に下がり、日が暮れるのも早くなる季節です。
子どもたちの体調や生活リズムが乱れやすく、園と家庭がしっかり連携することが欠かせません。
ここでは、11月ならではの保育と家庭とのつながり方を3つの視点で整理します。
11月特有の子どもの体調と生活リズムの変化
寒暖差が激しくなるこの時期は、子どもが風邪をひきやすくなります。
特に0~2歳児は体温調節が未熟なため、衣服の調整や体調観察が重要です。
園と家庭で「朝は少し鼻水が出ていた」などの小さな変化を共有することで、体調悪化を未然に防ぐことができます。
| 連携ポイント | 家庭への依頼例 |
|---|---|
| 衣服調整 | 「日中はまだ動くと汗をかきますので、着脱しやすい服装をご用意ください。」 |
| 体調観察 | 「少しでも元気がないときは、連絡帳や送迎時にお知らせいただけると助かります。」 |
季節行事や活動が増える時期の保護者協力
11月は作品展や収穫祭など、園行事が多くなる月です。
園と家庭が協力して素材を集めたり、生活習慣を整えたりすることで、子どもたちは安心して参加できます。
「家庭でのちょっとした準備」が園での体験をより豊かにするという視点が大切です。
| 行事の種類 | 家庭への依頼例文 |
|---|---|
| 作品展 | 「どんぐりや松ぼっくりなど、秋の自然素材を一緒に集めていただけますか?」 |
| 収穫祭 | 「旬の野菜や果物に触れる活動をします。家庭でも一緒に調理や食事を楽しんでみてください。」 |
感染症・安全面での注意喚起と連携の必要性
インフルエンザや胃腸炎などが流行しやすいのも11月の特徴です。
園だけでなく、ご家庭でも予防の意識を共有することが大切です。
また、日没が早いため、送迎時の交通安全にも配慮が必要です。
| 連携テーマ | 家庭への声かけ例 |
|---|---|
| 感染症対策 | 「園では手洗い・うがいを徹底しています。ご家庭でも同じ習慣を続けていただけると安心です。」 |
| 交通安全 | 「夕方は暗くなるのが早いので、送迎時には反射材付きのバッグや服をおすすめします。」 |
年齢別に見る11月の家庭との連携例文
子どもの発達段階によって、家庭への声かけや依頼の内容は少しずつ変わっていきます。
ここでは0歳から5歳までの年齢別に、11月に使える具体的な「例文」をまとめました。
保育通信や連絡帳にそのまま活用できるフレーズも多いので、参考にしてください。
0歳児クラス向けの依頼・声かけ例
0歳児は体温調節が難しく、感染症の影響を受けやすい時期です。
家庭との細やかな情報共有が特に重要になります。
| テーマ | 例文 |
|---|---|
| 衣服 | 「朝晩の冷え込みに備えて、着脱しやすい上着や靴下をご用意ください。」 |
| 体調 | 「鼻水や咳が見られたら、連絡帳や送迎時にお知らせいただけると助かります。」 |
| 離乳食 | 「園での食事の様子を随時お伝えします。ご家庭での変化やご心配な点があれば教えてください。」 |
1歳児クラス向けの依頼・声かけ例
自分で歩いたり遊んだりすることが増える時期です。
衣服の準備や感染症予防で、家庭との協力が欠かせません。
| テーマ | 例文 |
|---|---|
| 衣服 | 「動きやすく、着脱しやすい服装を準備していただけると助かります。」 |
| 体調 | 「寒暖差で体調を崩しやすいので、体温や食欲の変化を共有していただけると安心です。」 |
| 感染症 | 「園ではうがい・手洗いを取り入れています。ご家庭でも一緒に習慣づけをお願いします。」 |
2歳児クラス向けの依頼・声かけ例
自立心が芽生え、トイレトレーニングが進む時期です。
園と家庭で一貫性のあるサポートを行うことが大切です。
| テーマ | 例文 |
|---|---|
| 衣服 | 「寒さ対策をしながら、自分で着脱できる服装を選んでいただけると練習につながります。」 |
| 排泄 | 「園でのトイレの様子をお伝えしますので、ご家庭でも同じ声かけをしていただけると励みになります。」 |
| 安全 | 「夕方は暗くなるのが早いため、送迎時は周囲に気をつけていただければと思います。」 |
3歳児クラス向けの依頼・声かけ例
行事や活動に意欲的に取り組めるようになる時期です。
家庭での協力が活動の充実につながります。
| テーマ | 例文 |
|---|---|
| 衣服 | 「一人で着替えやすい服装をご準備いただき、自立を応援していきたいと思います。」 |
| 活動 | 「製作活動に使用するどんぐりや落ち葉を、週末にお子さんと一緒に集めていただけますか?」 |
| 安全 | 「暗くなるのが早いため、送迎時は反射材つきのバッグや服装がおすすめです。」 |
4歳児クラス向けの依頼・声かけ例
活動の幅が広がり、心身の成長が大きく見られる時期です。
保護者との協力が、挑戦や学びを支えます。
| テーマ | 例文 |
|---|---|
| 防寒 | 「登園時には帽子や手袋などを準備いただき、健康に過ごせるようにご協力ください。」 |
| 製作活動 | 「家庭で集めた落ち葉や木の実を作品づくりに活用しています。ぜひ一緒に探してみてください。」 |
| 健康 | 「乾燥する季節ですので、のどや肌の保湿にもご配慮いただけると安心です。」 |
5歳児クラス向けの依頼・声かけ例
小学校入学を控え、家庭と園で子どもの成長を共有する機会が増える時期です。
日々の生活習慣やイベントを通じて、自立を育んでいきます。
| テーマ | 例文 |
|---|---|
| 成長の共有 | 「参観や面談でお子さんの園での姿をお伝えします。ご家庭での様子もぜひお聞かせください。」 |
| 行事 | 「収穫祭では子どもたちと一緒に秋の実りを味わいます。ご家庭でも旬の食材に触れてみてください。」 |
| 安全 | 「夕方の送迎は暗いため、反射材のご使用や交通安全へのご配慮をお願いいたします。」 |
保育通信や連絡帳に使える11月の文例集
11月は体調や衣服の調整、感染症の流行、そして行事が重なる時期です。
ここでは、家庭へのお便りや連絡帳にそのまま活用できる「文例」をテーマごとにまとめました。
伝えたいことをシンプルに、でも温かみを持って書くのがポイントです。
体調・衣服に関する依頼文例
寒暖差の大きい時期には、子どもが快適に過ごせる衣服や健康管理の協力が必要です。
| シーン | 文例 |
|---|---|
| 衣服 | 「朝晩の冷え込みが強くなってきました。着脱しやすい服装での登園にご協力ください。」 |
| 体調変化 | 「咳や鼻水など、体調に変化があるときは連絡帳や送迎時にお知らせください。」 |
| 予防 | 「体調を崩しやすい季節です。家庭でも十分な睡眠と食事を心がけていただければ安心です。」 |
食事・生活習慣に関する共有文例
食育や生活リズムの安定は、園と家庭が協力することでより効果的になります。
| シーン | 文例 |
|---|---|
| 食事 | 「園での給食では苦手な野菜にも挑戦しています。ご家庭での様子もぜひ教えてください。」 |
| 睡眠 | 「夜更かしが続くと日中の活動に影響します。規則正しい生活リズムづくりにご協力ください。」 |
| 生活習慣 | 「朝ごはんをしっかり食べることで、一日の活動が元気にスタートできます。ぜひ意識してみてください。」 |
行事や活動に関する協力依頼文例
秋の自然を活かした活動や園のイベントには、家庭での協力が欠かせません。
| シーン | 文例 |
|---|---|
| 作品展 | 「制作活動に使うどんぐりや落ち葉などを、お子さんと一緒に集めてきていただけると助かります。」 |
| 収穫祭 | 「収穫祭では旬の野菜を使います。家庭でも一緒に秋の味覚を楽しんでみてください。」 |
| 発表会 | 「園で練習を重ねています。ご家庭でも『がんばってるね』と声をかけていただけると励みになります。」 |
安全・感染症に関する注意喚起文例
健康と安全を守るためには、園と家庭で一貫した取り組みを行うことが大切です。
| シーン | 文例 |
|---|---|
| 感染症 | 「インフルエンザが流行しやすい時期です。ご家庭でも手洗い・うがいの習慣をお願いします。」 |
| 乾燥対策 | 「乾燥が強まり、肌やのどの不調が増える時期です。保湿や加湿を意識していただければ安心です。」 |
| 交通安全 | 「夕方は暗くなるのが早いです。送迎時には反射材のご利用や車の安全確認をお願いいたします。」 |
家庭との連携を深めるための工夫
日々の連絡やイベント協力だけでなく、保護者との信頼関係を育む小さな工夫が大切です。
ここでは、家庭とのつながりをさらに強めるための具体的なアイデアをご紹介します。
送迎時・連絡帳・アプリ活用のポイント
家庭とのコミュニケーションは「ちょっとした一言」で深まります。
送迎のタイミングや連絡帳に、子どもの成長を短くても共有することが信頼につながります。
| 方法 | 工夫例 |
|---|---|
| 送迎時 | 「今日は絵本を最後まで聞けましたよ。」など短いエピソードを伝える |
| 連絡帳 | 体調だけでなく「友だちとブロック遊びを楽しんでいました」とポジティブな一言を添える |
| アプリ | 写真や動画で日中の様子を共有し、家庭でも会話が広がるきっかけにする |
保護者との信頼関係を育むコミュニケーション
保護者も「自分の声を聞いてもらえている」と感じられると安心します。
意見や要望を受け止める姿勢が、園と家庭の信頼を築く第一歩です。
| ポイント | 実践例 |
|---|---|
| 傾聴 | 保護者の話を途中で遮らず、最後まで聞く姿勢を大切にする |
| 共感 | 「そうですよね、朝の準備は大変ですよね。」と気持ちに寄り添う言葉を返す |
| 共有 | 園での対応や工夫を伝え、家庭と一緒に解決方法を探す |
園と家庭が一体となる環境づくりの実践例
園と家庭が「パートナー」として取り組むことで、子どもに安心感が生まれます。
小さな共同作業が信頼関係を大きく育てると意識しましょう。
| 取り組み | 具体例 |
|---|---|
| 自然素材集め | 週末に家庭で集めたどんぐりや落ち葉を持ち寄り、園で作品にする |
| 家庭での課題 | 「寝る前に好きな絵本を1冊読む」など簡単にできる取り組みをお願いする |
| 季節行事 | 収穫祭や作品展で家庭と園が一緒に子どもの成長を喜ぶ |
まとめと11月の家庭連携の心構え
11月は寒さが増し、感染症や生活リズムの乱れが起こりやすい季節です。
同時に、収穫祭や作品展など、子どもたちの成長を感じられる行事も多くあります。
だからこそ、園と家庭が一緒に連携し、子どもを中心に支えていく姿勢が大切です。
| ポイント | 心構え |
|---|---|
| 健康管理 | 「衣服・体調・睡眠」の3つを家庭と園で共有し、子どもを守る |
| 保護者協力 | 作品づくりや行事参加を通して、家庭も園の活動に関わる |
| 信頼関係 | 小さな報告や声かけを積み重ね、家庭と園の距離を近づける |
連携の目的は「情報を伝えること」ではなく「子どもを一緒に育てること」です。
保護者との信頼を育みながら、子どもが安心して成長できる環境を整えていきましょう。
園と家庭が同じ方向を向いたとき、子どもの体験はより豊かで深いものになります。