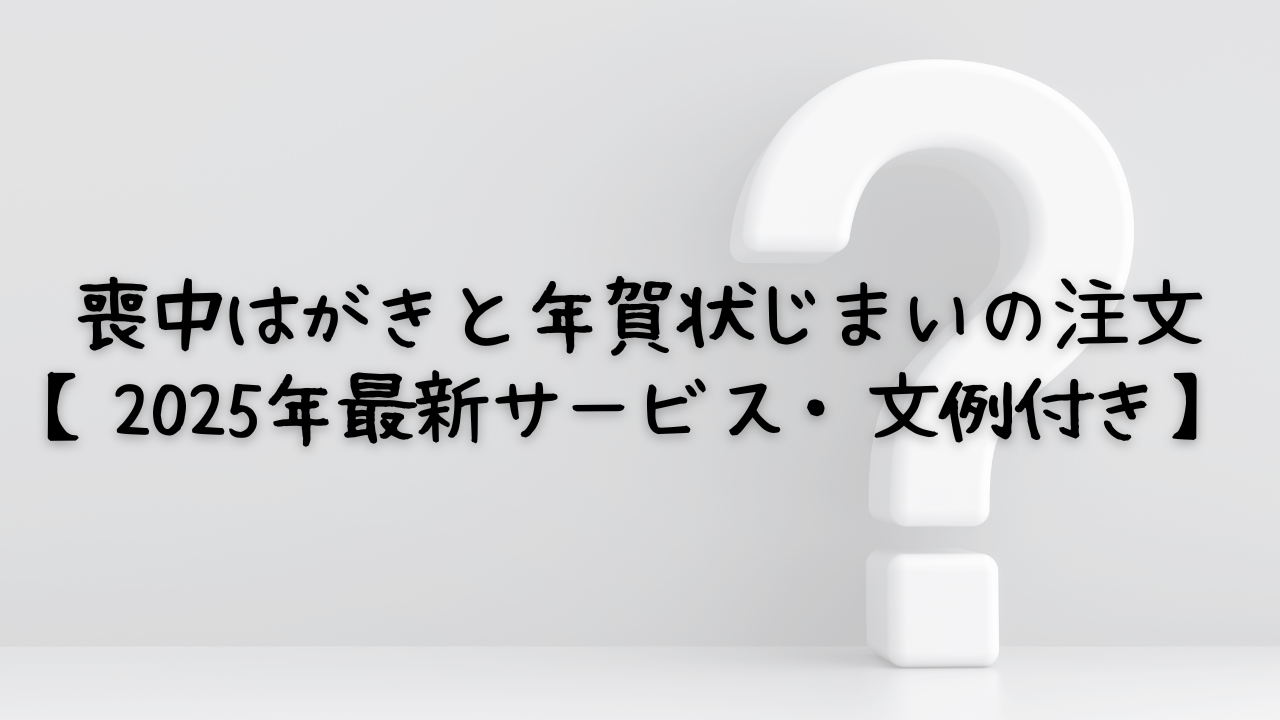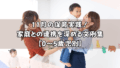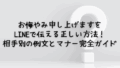喪中はがきや年賀状じまいは、相手への感謝や配慮を込めながら、新年のご挨拶に関する気持ちを伝える大切な手段です。
近年はネット注文の普及により、スマホから簡単にデザイン選びや宛名印刷、投函まで完了できるサービスが主流となりました。
本記事では、「喪中はがき」と「年賀状じまい」の基本的な意味や違い、注文の流れ、2025年におすすめのネット印刷サービス、文例やマナー、最新トレンドまでを網羅的に解説しています。
「喪中はがきを出すべきか」「年賀状じまいを検討したい」など迷っている方にとって、自分に合った選択肢を見極めるヒントがきっと見つかります。
大切な人とのご縁を大事にしながら、便利で安心できる方法で準備を進めてみませんか。
喪中はがきと年賀状じまいの基礎知識
この章では、「喪中はがき」と「年賀状じまい」がそれぞれどのような意味を持つのかを整理します。
まずは言葉の定義と背景を知ることで、どちらを選ぶべきか迷わない土台が作れます。
喪中はがきとは何か?意味と背景
喪中はがきは、近親者が亡くなった際に「新年のご挨拶(年賀状)をご遠慮します」という気持ちを伝える挨拶状です。
一般的には2親等以内(両親・祖父母・兄弟姉妹・子どもなど)の不幸があった場合に出すことが多いです。
日本では昔から、身内の死を悼む期間を「喪中」と呼び、その間は慶事を控える習慣がありました。
喪中はがきはこの文化を背景に、相手に余計な気遣いや誤解を与えないように配慮して送られています。
つまり、喪中はがきはマナーと心遣いの両方を兼ね備えた大切な挨拶状なのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる不幸 | 2親等以内が一般的 |
| 送る目的 | 新年の挨拶を控えることを事前に伝える |
| 送る時期 | 10月〜12月初旬 |
年賀状じまいとは?選ばれる理由と近年の増加傾向
年賀状じまいは、これまで続けてきた年賀状のやりとりを終了する旨を、感謝の気持ちを込めて伝える挨拶です。
「高齢になったので体力的に難しい」「SNSやメール中心に移行したい」「年賀状の価格高騰で負担を減らしたい」など、背景は人それぞれです。
近年は特に高齢層を中心に広がっており、人生の節目の選択として選ばれるケースが増えています。
年賀状じまいは「人付き合いの終わり」ではなく「挨拶方法の変化」だと理解してもらうことが大切です。
| 理由 | 具体例 |
|---|---|
| 年齢や体調 | 高齢になった、病気で準備が難しい |
| ライフスタイル | SNSやメールで代替する |
| 経済的理由 | はがき代や印刷代の負担を軽減したい |
喪中はがきと年賀状じまいの違いと使い分け
喪中はがきと年賀状じまいは、どちらも「新年の挨拶に関する特別なお知らせ」ですが、目的やタイミングは大きく異なります。
この章では、2つの違いを明確にし、どのように使い分ければよいかを解説します。
目的と伝える内容の違い
喪中はがきは不幸があったことを伝えつつ、新年の挨拶を遠慮するために送ります。
一方で年賀状じまいは年賀状のやり取り自体を終了する意思を示すために送るものです。
つまり、喪中はがきは「今年だけの一時的なお知らせ」、年賀状じまいは「今後ずっと続けないという意思表示」という違いがあります。
混同しないように、それぞれの役割を理解することが大切です。
| 種類 | 目的 | 伝える内容 |
|---|---|---|
| 喪中はがき | 喪中につき新年の挨拶を控える | 誰がいつ亡くなったか、欠礼の挨拶、感謝の言葉 |
| 年賀状じまい | 今後の年賀状やり取りを終了する | 感謝、終了の旨、今後の関係継続への願い |
出す時期・タイミングの違い
喪中はがきは、相手が年賀状を書く前に届くように出すのが基本です。
具体的には10月〜12月初旬が理想で、遅れてしまった場合は「寒中見舞い」で対応します。
年賀状じまいは、人生の節目やライフスタイルの変化に合わせて、自分のタイミングで出せます。
「今年で最後にします」と宣言する場合は年賀状で伝えることも可能ですし、年末に専用の挨拶状として送る方法もあります。
喪中はがきは“急なお知らせ”、年賀状じまいは“計画的な告知”とイメージすると分かりやすいです。
| 種類 | 出す時期 | タイミングのポイント |
|---|---|---|
| 喪中はがき | 10月〜12月初旬 | 相手が年賀状を準備する前に届くように |
| 年賀状じまい | 任意(節目や事情に応じて) | 年末に挨拶状として送るか、最後の年賀状に記載 |
喪中はがき・年賀状じまいの注文方法
ここでは、喪中はがきや年賀状じまいを準備する際の注文方法について解説します。
近年はネットサービスが主流ですが、従来の店舗注文や郵便局サービスも根強く利用されています。
それぞれの特徴を理解して、自分に合った注文方法を選びましょう。
ネット注文の流れと基本ステップ
最も利用されているのがインターネット注文です。
スマホやパソコンからデザインを選び、文例を入力して申し込むだけで、短期間で仕上がります。
基本的な流れは以下の通りです。
- 公式サイトでデザインを選ぶ
- 文例や挨拶文を入力・編集する
- 宛名印刷や投函代行のオプションを設定する
- 注文内容を確認して支払い方法を選ぶ
- 最短で翌営業日に発送
最近は会員登録なしで注文可能、スマホだけで完結、少ない枚数から注文できるといった便利な仕組みも増えています。
ネット注文はスピードと手軽さを両立した最も効率的な方法です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 24時間いつでも注文できる | 現物を見て選べない |
| 文例やデザインが豊富 | 操作に慣れが必要な場合も |
| 宛名印刷・投函代行で手間が減る | 配送日程に余裕を持つ必要あり |
店舗・郵便局での注文方法
ネットを利用しない場合は、写真店・印刷所・郵便局などでの注文も可能です。
特に郵便局では「喪中はがき印刷サービス」や「年賀状じまい向け文例テンプレート」が用意されており、手軽に依頼できます。
店舗注文では実際の見本を手に取れるため、デザインや紙質を確認したい人に向いています。
ただし、店舗に出向く手間や営業時間の制約があるため、事前に余裕を持って準備することが必要です。
| 注文方法 | 特徴 |
|---|---|
| 写真店・印刷所 | デザイン見本を手に取って確認できる |
| 郵便局 | 全国どこでも利用可能で、投函まで任せられる |
注文時に気を付けたいチェックポイント
注文方法にかかわらず、以下の点を事前に確認しておくと安心です。
- 宛名データの準備:ExcelやCSVでまとめておくと効率的
- 納期:年末に近づくほど混み合うため、早めの注文が安心
- 割引情報:早割キャンペーンを活用すると費用を抑えられる
- 文例チェック:誤字脱字やマナー違反がないか確認
スムーズな注文の鍵は「早めの準備」と「宛名の整理」です。
| チェック項目 | 理由 |
|---|---|
| 宛名リストの整理 | 入力ミスや重複を防ぐ |
| 注文時期 | 納期遅れを防ぎ、早割で節約できる |
| 文例確認 | 相手に失礼がないようにする |
2025年におすすめのネット印刷サービス
喪中はがきや年賀状じまいを準備するなら、信頼できるネット印刷サービスを選ぶことが大切です。
ここでは、2025年の最新トレンドを踏まえて「スピード」「デザイン」「コスパ・サポート」の3つの観点から、おすすめの選び方を紹介します。
スピード重視で選ぶサービス
急な不幸や、年末ぎりぎりに準備する場合は納期の早さが重要です。
多くの大手サービスでは「最短翌営業日発送」に対応しており、中には15時までの注文で当日出荷に対応するところもあります。
スピードを優先するなら、出荷までの日数と配送方法を必ず確認しておきましょう。
| サービス名 | 特徴 |
|---|---|
| Webポ(郵便局系) | 最短翌営業日出荷、投函代行も対応 |
| 挨拶状ドットコム | スピード印刷、文例テンプレートが豊富 |
| 楽天系サービス | 注文締切が遅めで、急な注文にも対応 |
デザインの豊富さで選ぶサービス
文例の内容と同じくらい大切なのがデザインです。
シンプルで落ち着いた喪中はがきから、和モダンや写真入りデザインまで、サービスによって個性が異なります。
特に年賀状じまいは「これまでのお付き合いに感謝」を表すため、温かみのあるデザインを選ぶ人が増えています。
デザインの選択肢が多いサービスほど、自分や家族に合った雰囲気を見つけやすいです。
| サービス名 | デザイン傾向 |
|---|---|
| カードボックス | 和風・モダンをバランス良く用意 |
| ハッピーカード | 上品で落ち着いた雰囲気が多い |
| カメラのキタムラ | 写真入り対応、華やかさと柔らかさを両立 |
コスパとサポートで選ぶサービス
大量注文や初めての利用なら価格とサポートも重視すべきポイントです。
早割やまとめ割を活用すれば、1枚あたりの単価を大きく下げられます。
また、マナー監修の文例集やサポート窓口があるサービスは、初めての注文でも安心です。
「安さ」だけでなく「安心感」も含めてコスパを考えるのがポイントです。
| サービス名 | 特徴 |
|---|---|
| ネットスクウェア | 早割が豊富で安価、コスパ重視に最適 |
| 日本郵便(郵便局の公式) | 信頼性が高く、窓口相談も可能 |
| パレットプラザ | 店舗サポートとネット注文を両立 |
喪中はがき・年賀状じまいの文例集
実際に挨拶状を作成する際、最も迷うのが「文例」です。
ここでは、喪中はがきと年賀状じまい、それぞれのケースに合わせた具体的な文例を紹介します。
そのまま使うのではなく、自分の状況に合わせてアレンジするのが理想です。
喪中はがきの文例(親・配偶者・祖父母の場合)
喪中はがきは、誰が亡くなったかを簡潔に伝えつつ、感謝の言葉を添えるのが基本です。
親が亡くなった場合
本年六月に父 ○○○○ が八十五歳にて永眠いたしました。
生前賜りましたご厚情に深く御礼申し上げます。
つきましては新年のご挨拶をご遠慮申し上げます。
配偶者が亡くなった場合
本年三月に夫 ○○○○ が七十二歳にて永眠いたしました。
ここに謹んでご通知申し上げますとともに、明年の年始のご挨拶を失礼させていただきます。
祖父母が亡くなった場合
去る十月に祖母 ○○○○ が九十歳にて永眠いたしました。
生前に賜りましたご厚誼に心より感謝申し上げます。
新年のご挨拶をご遠慮させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
喪中はがきは事実を簡潔に伝え、余計な表現を避けることがマナーです。
| 構成要素 | 内容 |
|---|---|
| 誰が亡くなったか | 故人の続柄・氏名 |
| 時期 | 亡くなった月 |
| 挨拶 | 新年の挨拶を控える旨と感謝の言葉 |
年賀状じまいの文例(高齢・転居・デジタル移行の場合)
年賀状じまいは「これまでのお付き合いに感謝」+「今後は別の方法で交流」の2点を入れると好印象です。
高齢を理由にする場合
長年にわたり年賀状のやり取りをいただき誠にありがとうございました。
高齢となり筆を執ることが難しくなりましたため、本年をもちまして年賀状によるご挨拶を控えさせていただきます。
今後とも変わらぬご厚誼をお願い申し上げます。
転居を理由にする場合
私事で恐縮ですが、このたび転居をいたしました。
これを機に年賀状でのご挨拶を終了させていただくことといたしました。
今後はメールやお電話にて近況をお伝えできれば幸いです。
デジタル移行を理由にする場合
旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました。
今後はメールやSNSにて新年のご挨拶をさせていただくことといたします。
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
年賀状じまいは「人間関係を終わらせる」ものではなく、「方法を変える」ものだと示すのが大切です。
| 理由 | 文例の特徴 |
|---|---|
| 高齢 | 体力的に難しいことを丁寧に伝える |
| 転居 | 生活環境の変化を理由にする |
| デジタル移行 | 今後も交流を続けたい意思を明確にする |
喪中はがきと年賀状じまいを兼ねる場合の文例
両方を同時に伝えたい場合は、文面を工夫する必要があります。
例文:
去る九月に母 ○○○○ が八十七歳にて永眠いたしました。
ここに謹んでご通知申し上げますとともに、年末年始のご挨拶を控えさせていただきます。
併せまして、本年をもちまして年賀状による新年のご挨拶も終了させていただく所存です。
今後とも変わらぬご交誼のほどよろしくお願い申し上げます。
「喪中につき新年のご挨拶を控える」と「来年以降の年賀状を終了する」という2つを、バランスよく伝えることがポイントです。
| 文例の要点 | ポイント |
|---|---|
| 喪中の通知 | 誰が亡くなったかを明記 |
| 欠礼の挨拶 | 新年の挨拶を控える旨を伝える |
| 年賀状じまいの告知 | 今後も交流を続けたい気持ちを添える |
マナーと最新トレンド
喪中はがきや年賀状じまいは、相手への配慮が何より大切です。
ここでは、よくあるマナー違反を避けるための注意点と、2025年ならではの最新トレンドを紹介します。
喪中はがきのマナーと注意点
喪中はがきは「簡潔さと誠実さ」が基本です。
余計な装飾や句読点を避け、丁寧にまとめることが求められます。
- 送る範囲:年賀状をやり取りしている人すべてに送るのが原則
- 送る時期:12月上旬までに届くように投函する
- 遅れた場合:新年を迎えてからは「寒中見舞い」で代替
特に注意すべきは「出す時期」です。 年末ぎりぎりになると、相手がすでに年賀状を書いてしまっている可能性があります。
余裕を持った準備が相手への思いやりにつながります。
| ポイント | NG例 |
|---|---|
| 句読点を使わない | 「。」や「、」を文中に入れる |
| 早めに送る | 12月下旬に投函する |
| 寒中見舞いで対応 | 喪中はがきを年明けに送る |
年賀状じまいで誤解されないための工夫
年賀状じまいは、一歩間違えると「もう付き合いたくない」という印象を与えてしまう可能性があります。
そのため、感謝の言葉と今後の交流意欲を必ず入れるのが鉄則です。
- 感謝を伝える:「これまでのお付き合いに感謝申し上げます」と明記する
- 今後の交流を示す:「今後はメール等で近況をお伝えできれば幸いです」と添える
- 理由を簡潔に:「高齢」「体調」「生活スタイルの変化」などシンプルに
「じまい」は終わりではなく、形を変えた続きであることを伝えることが大切です。
| 良い例 | 悪い例 |
|---|---|
| 「今後は別の形でご挨拶を続けたい」 | 「もう年賀状は出しません」 |
| 「これまでに感謝」 | 理由を一切書かない |
2025年の最新トレンド(ネット注文・デザイン傾向など)
2025年現在、喪中はがき・年賀状じまいを取り巻く環境には大きな変化があります。
- ネット注文が主流:スマホだけで完結できるサービスが急増
- 便利な機能:宛名印刷・投函代行・最短翌日出荷がほぼ標準化
- デザインの多様化:和モダン、シンプル、ナチュラル系など幅広く選べる
- 環境配慮:再生紙やカーボンオフセット対応のはがきが登場
今は「早い・便利・多様性」の3拍子が揃ったサービスが当たり前になりつつあります。
| トレンド | 特徴 |
|---|---|
| ネット注文 | スマホ完結・投函代行が標準 |
| デザイン傾向 | 和モダン・ナチュラル・写真入り |
| エコ対応 | 再生紙・環境配慮型印刷 |
まとめとこれからの選び方
ここまで、喪中はがきと年賀状じまいの違いから、注文方法・文例・マナー・最新トレンドまでを紹介しました。
最後に、自分に合った方法を選ぶための視点を整理してみましょう。
自分に合った方法を見極めるポイント
喪中はがきと年賀状じまいは、どちらも「人との関係を大切にする気持ち」を表すものです。
自分や家族の状況に合わせて、どちらを選ぶべきかを判断しましょう。
- 喪中はがき:近親者が亡くなり、その年だけ年賀状を控える場合
- 年賀状じまい:ライフスタイルの変化や高齢を理由に、年賀状のやりとりを終了する場合
- 併用:喪中を機に、年賀状じまいを同時に伝えたい場合
大切なのは「相手に誤解を与えず、感謝の気持ちをしっかり伝える」ことです。
| 選択肢 | 適したケース |
|---|---|
| 喪中はがき | 一時的に年賀状を控える必要がある場合 |
| 年賀状じまい | これから先ずっと年賀状をやめたい場合 |
| 併用 | 喪中のタイミングで年賀状も終了したい場合 |
ネットサービスを活用して安心・便利に準備する
2025年の現在では、喪中はがき・年賀状じまいの多くがネットで注文可能です。
宛名印刷や投函代行、豊富なデザインテンプレートを活用すれば、時間も手間も大幅に削減できます。
さらに、早割やキャンペーンを利用すれば費用も抑えられます。
ただし、注文が年末に近づくと混雑や納期遅延のリスクがあります。 早めに準備しておくのが安心です。
「早めの準備」と「信頼できるサービスの選択」こそが、満足のいく挨拶状づくりの最大のコツです。
| ネット注文の利点 | 注意点 |
|---|---|
| 24時間注文可能 | 配送日程に余裕を持つ必要あり |
| 文例やデザインが豊富 | 現物を確認できない |
| 宛名印刷・投函代行が便利 | 誤入力がないか要チェック |