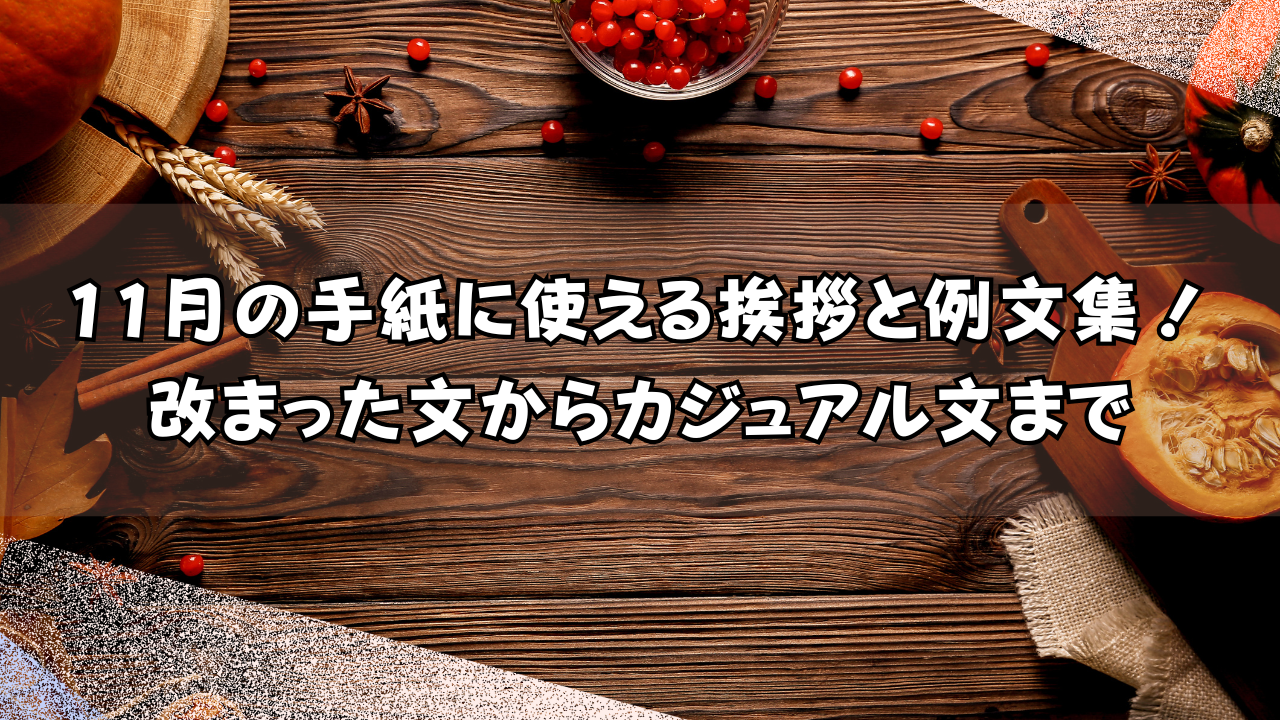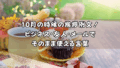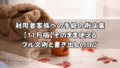11月は紅葉や木枯らし、初霜など季節の移ろいが色濃く表れる時期です。
この季節ならではの挨拶を手紙に添えることで、相手に四季の趣と心遣いを伝えることができます。
本記事では、「手紙 11月 挨拶 例文」を探している方に向けて、改まった文から親しい人へのカジュアルな表現、さらにビジネスで使える例文まで幅広くご紹介します。
また、11月らしい季語や慣用句、安否をたずねる言葉や結びの表現など、シーン別にすぐ使えるフルバージョン文例を多数掲載しました。
手紙の冒頭や結びに入れるだけで使える文例がそろっているので、どなたでも安心して活用できます。
季節感あふれる挨拶で、大切な人や取引先に心温まるメッセージを届けましょう。
11月の手紙にふさわしい挨拶とは?
11月は秋から冬への変わり目であり、紅葉や木枯らし、霜など自然の変化を強く感じる時期です。
この季節ならではの挨拶を手紙に添えることで、相手に四季の趣と自分の思いやりを伝えることができます。
ここでは、11月の季節感を反映した表現や、手紙での挨拶が持つ役割について見ていきましょう。
11月の季節感と和名「霜月」の意味
11月は和名で「霜月(しもつき)」と呼ばれます。
これは、霜が降りる季節に由来しており、暦の上でも冬の始まりにあたります。
紅葉が見ごろを迎え、木枯らしが吹き、日ごとに寒さが増していく情景を言葉にすると、手紙に深みが加わります。
| 11月を表す言葉 | 意味 |
|---|---|
| 霜月 | 霜が降り始める月 |
| 晩秋 | 秋の終わりを示す表現 |
| 立冬 | 暦の上で冬に入る節目 |
「霜月」という言葉を取り入れるだけで、手紙がぐっと11月らしい雰囲気になります。
手紙に季節の挨拶を添える重要性
手紙の冒頭や結びに時候の挨拶を入れるのは、日本独特の文化です。
11月の挨拶では、紅葉や木枯らしといった自然の移ろいを描写することで、文章に彩りを加えられます。
さらに、体調を気づかう言葉を添えれば、相手への思いやりがより強く伝わります。
| ポイント | 効果 |
|---|---|
| 季節感を表現する | 手紙に趣が出て印象的になる |
| 相手を気づかう表現を加える | 温かみのある文章になる |
| 自然な言葉を選ぶ | 堅苦しくなりすぎず読みやすい |
特にビジネスや改まった手紙では、相手の健康や安否を気づかう一文が欠かせません。
11月は寒暖差も大きいため、「お風邪など召されていませんか」といった配慮の言葉を加えると効果的です。
11月の手紙で使える代表的な挨拶【例文付き】
11月の手紙には、改まった表現から親しみやすい言葉まで幅広い挨拶が使えます。
ここでは、改まった手紙・親しい人向け・ビジネス文書の3パターンに分けて例文をご紹介します。
状況や相手に応じて使い分けましょう。
改まった手紙向けの正式な挨拶
フォーマルな文面では、季語や慣用句を用いて格調高い表現を心がけます。
「晩秋の候」「立冬の候」などがよく用いられます。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 「晩秋の候、皆様にはお変わりなくご健勝のこととお喜び申し上げます。」 | 改まった挨拶状や目上の方への手紙 |
| 「立冬を過ぎ、寒さも一段と深まってまいりました。皆様、お健やかにお過ごしでしょうか。」 | 時候の便り、ビジネスレター |
| 「紅葉も見ごろを迎え、錦秋の美しい季節となりました。」 | お礼状や改まった季節の挨拶 |
改まった文例では、冒頭で季節を描写し、その後に相手の健康や繁栄を祈る一文を添えるのが基本です。
親しい相手に使えるカジュアルな挨拶
家族や友人に宛てる手紙では、日常的な季節の表現が喜ばれます。
気軽に読めるように、口語的な書き出しにするのがおすすめです。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 「紅葉が美しく染まり、散歩が楽しい季節になりました。」 | 友人や知人への便り |
| 「朝夕めっきり冷え込むようになりましたが、お元気ですか。」 | 家族や親しい人への手紙 |
| 「日だまりが恋しい頃となりました。いかがお過ごしでしょうか。」 | 親しみを込めた近況報告 |
親しい相手には、形式ばらず「元気ですか」「いかがお過ごしですか」といった素直な言葉で十分です。
ビジネス文書にふさわしい挨拶
ビジネスシーンでは、礼儀正しく、簡潔で分かりやすい挨拶が求められます。
取引先や職場の上司に送る際は、過度に華美にならず落ち着いた表現を心がけましょう。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 「木々の葉が散りゆく季節となりましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。」 | ビジネスレター全般 |
| 「立冬を迎え、日ごとに寒さが加わってまいりました。貴社ますますご隆盛のことと拝察いたします。」 | 企業間の書簡 |
| 「暮秋の候、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。」 | 感謝や依頼を伝える文書 |
ビジネスでは「ご健勝」「ご隆盛」「ご清祥」といった定型的な表現を使うと安心です。
11月の安否をたずねるフレーズ集
11月は寒暖差が大きく、体調を崩しやすい季節です。
手紙に安否をたずねる言葉を添えることで、相手を思いやる気持ちを自然に伝えることができます。
ここでは、体調を気づかう表現や家族・周囲を思いやるフレーズをご紹介します。
体調を気づかう言葉
冷え込みや風邪の流行を意識した一言を入れると、心温まる印象を与えられます。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 「寒さが増してきましたが、お元気でお過ごしでしょうか。」 | 一般的な安否の確認 |
| 「体調など崩されていませんか。」 | フォーマルにもカジュアルにも使用可 |
| 「風邪が流行る季節ですが、どうぞご自愛ください。」 | 健康を気づかう言葉 |
「ご自愛ください」という表現は、改まった手紙でもカジュアルな手紙でも幅広く使える万能フレーズです。
家族や周囲を思いやる言葉
相手本人だけでなく、ご家族や周囲の方の健康を気づかう言葉を添えると、さらに丁寧な印象を与えられます。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 「ご家族の皆様はお変わりなくお元気でいらっしゃいますか。」 | 親族や親しい方への手紙 |
| 「お忙しい時期かと存じますが、皆様健やかにお過ごしのことと拝察いたします。」 | ビジネス・改まった文面 |
| 「寒さが厳しくなってまいりましたが、ご家族の皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。」 | 季節感を込めた気づかい |
特に改まった手紙では「ご家族の皆様」という言葉を入れると、丁寧さが増します。
安否をたずねるフレーズは、手紙の本題に入る前に添えると、優しさが伝わりやすくなります。
11月にふさわしい結びの挨拶【例文付き】
手紙の最後に添える結びの挨拶は、文章全体を締めくくる大切な要素です。
11月は冬の入り口でもあるため、寒さや体調を気づかう言葉を添えると、相手への心遣いがより伝わります。
ここでは、改まった手紙・親しい人向け・ビジネス文書に分けて結びの例文をご紹介します。
改まった手紙での結び
フォーマルな手紙では、体調を気づかうと同時に、相手の幸福や繁栄を祈る表現が一般的です。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 「寒さ厳しくなってまいりますが、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。」 | 改まった挨拶状・お礼状 |
| 「これから日ごとに寒さが増してまいります。何卒ご自愛専一にてお過ごしください。」 | 季節の便り・フォーマルな場面 |
| 「師走を迎えるにあたり、お忙しい毎日かと存じますが、どうぞご健勝でありますようお祈りいたします。」 | 年末に向けた挨拶文 |
正式な結びでは「ご健勝」「ご多幸」「ご清祥」といった言葉を組み合わせると、格調高い印象を与えられます。
親しい人に向けたカジュアルな結び
親しい人に送る手紙では、リラックスした雰囲気の言葉を選びましょう。
健康を願う気持ちを素直に伝えると、温かみのある文章になります。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 「だんだんと冬が近づいています。風邪などひかれませんように。」 | 家族や友人への便り |
| 「温かくして、どうぞお体を大切にお過ごしくださいね。」 | 親しい友人や親族への手紙 |
| 「寒さが増しますので、お互い元気に冬を迎えましょう。」 | フランクな交流の手紙 |
親しい人への結びには、自然体で素直な表現を用いるのがコツです。
ビジネスシーンでの結び
ビジネス文書では、礼儀を重んじつつ簡潔にまとめることが求められます。
年末が近づく11月は、業務の繁忙期を意識した言葉を添えると好印象です。
| 例文 | 使いどころ |
|---|---|
| 「寒さが一段と厳しくなってまいりますが、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。」 | 取引先への手紙 |
| 「年末に向けご多忙のことと存じます。何卒ご自愛くださいませ。」 | 取引や依頼の文書 |
| 「向寒の折、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。」 | 一般的なビジネスレター |
ビジネスでの結びは「ご自愛くださいませ」や「ご発展をお祈り申し上げます」といった丁寧な言葉が基本です。
11月の手紙に役立つ季語・慣用句一覧
11月の手紙をより味わい深くするには、季節を感じさせる言葉や慣用句を活用するのが効果的です。
紅葉や木枯らし、初霜など、自然や行事を織り込むことで、相手に鮮やかな情景を思い浮かべてもらえます。
ここでは、11月ならではの季語や表現を整理しました。
紅葉・木枯らし・初霜など自然を表す言葉
自然を描写する言葉は、手紙に季節感を与えます。
紅葉や落葉といった視覚的な表現に加え、木枯らしや霜など体感的な言葉も使いやすいです。
| 季語 | 意味・使い方 |
|---|---|
| 紅葉(もみじ) | 「紅葉が見ごろを迎え」といった季節の描写に |
| 木枯らし | 「木枯らしが吹き、冬の足音を感じます」など体感的表現に |
| 初霜 | 「初霜の便りが聞かれる季節となりました」 |
| 小春日和 | 「小春日和の穏やかな日が続いております」など柔らかな表現に |
自然を表す季語は、書き出しや結びに入れるだけで文章全体が生き生きとします。
11月ならではの行事や風物詩の言葉
行事や習慣に触れると、手紙がより具体的で親しみやすくなります。
| 季語・風物詩 | 意味・使い方 |
|---|---|
| 七五三 | 「七五三を迎えられるお子様の健やかな成長をお祈りいたします」 |
| 菊花 | 「菊花の香り漂う季節となりました」 |
| 山茶花(さざんか) | 「庭先に山茶花が咲き始めました」など身近な描写に |
| 霜月 | 「霜月を迎え、寒さも深まってまいりました」 |
行事や花の名前を入れると、相手に身近な季節感を共有できます。
文例に使いやすい定番の慣用句
昔から手紙に用いられる慣用句は、改まった手紙にもカジュアルな手紙にも応用できます。
| 慣用句 | 用例 |
|---|---|
| 晩秋の候 | 「晩秋の候、皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます」 |
| 暮秋の候 | 「暮秋の候、ご家族皆様のご多幸をお祈り申し上げます」 |
| 向寒の候 | 「向寒の候、何卒ご自愛専一にてお過ごしください」 |
| 深冷の候 | 「深冷の候、寒さ厳しき折り、皆様のご健勝をお祈り申し上げます」 |
慣用句をうまく取り入れると、手紙が洗練された印象になります。
11月の具体的な手紙文例集【用途別】
ここでは、改まった手紙・親しい人への手紙・ビジネスで使える手紙の3パターンに分けて、すぐに使える文例をご紹介します。
フルバージョンの例文も掲載していますので、そのまま活用することも可能です。
改まった手紙の文例
改まった手紙では、形式に沿った挨拶・本題・結びを整えることが大切です。
| 場面 | 文例 |
|---|---|
| 一般的な改まった挨拶 | 拝啓 晩秋の候、皆様には益々ご清祥のことと心よりお喜び申し上げます。 さて、今年も残すところあと二か月となりました。 朝夕の冷え込みが厳しくなってまいりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。 日々ご多忙のことと存じますが、どうかご自愛専一にてお過ごしください。 向寒の折、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 敬具 |
| 年末を意識した改まった挨拶 | 拝啓 暮秋の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 早いもので、師走も目前となり、何かと慌ただしい時期を迎えました。 皆様におかれましては、引き続きご健康に留意され、良き年をお迎えになられますよう心よりお祈り申し上げます。 敬具 |
親しい人への手紙文例
親しい相手には、口語的で柔らかい表現を用いると、読みやすく親近感が伝わります。
| 場面 | 文例 |
|---|---|
| 友人への便り | こんにちは。紅葉がきれいに色づいてきましたね。 最近は朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたが、元気にしていますか。 こちらは家族みんな変わりなく過ごしています。 そちらも寒さに負けず、温かくしてお過ごしくださいね。 |
| 親族への便り | 朝晩めっきり冷え込むようになりました。 皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。 子どもたちは元気に学校へ通っております。 どうぞお体に気をつけて、冬を迎えられますように。 |
ビジネスで使える手紙文例
ビジネス文書では、簡潔かつ礼儀正しい表現が求められます。
相手への感謝や今後のお願いを、時候の挨拶に絡めると自然です。
| 場面 | 文例 |
|---|---|
| 一般的なビジネス挨拶 | 拝啓 木々の葉が散りゆく季節となりました。 平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 寒さが一段と厳しくなってまいりますので、どうぞご自愛ください。 敬具 |
| 取引先への依頼文 | 拝啓 立冬を迎え、朝夕の寒気が身にしみる季節となりました。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、○○の件につきましてお願い申し上げたく、ご連絡差し上げました。 何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。 敬具 |
用途別のフルバージョン例文をそのまま使えば、初めてでも安心して手紙が書けます。
ワンランク上の手紙を書くコツ
同じ11月の挨拶でも、一工夫するだけで相手により深い印象を残すことができます。
ここでは、気候や相手に合わせた表現の工夫を紹介します。
形式的な定型文だけでなく、自分らしい言葉を添えることが大切です。
その年の気候や出来事を取り入れる
一般的な季語だけでなく、その年の気候の特徴や社会的な出来事を交えると、オリジナリティが増します。
例えば「今年は例年より冷え込みが早いようですね」といった具体的な言葉を入れると、相手にリアルさが伝わります。
| 工夫例 | 効果 |
|---|---|
| 「例年になく冷え込みが厳しい11月ですね」 | その年らしい季節感を共有できる |
| 「暖冬の影響か、紅葉が遅れているように感じます」 | 実際の気候に基づくリアリティが出る |
| 「七五三のお祝いで街が華やいでいますね」 | 季節行事を共有できる |
ニュースや地域の出来事を取り入れると、相手が「自分のために書かれた手紙だ」と感じやすくなります。
季語やフレーズを相手に合わせて選ぶ
手紙を受け取る相手に合わせて、季語やフレーズを変えると、より伝わりやすい文章になります。
例えば、目上の方には格式ある表現を、友人や家族には柔らかい言葉を選びましょう。
| 相手 | おすすめの表現 |
|---|---|
| 目上の方 | 「晩秋の候、ご清祥のこととお喜び申し上げます」 |
| 友人 | 「日だまりが恋しい季節になりましたね。お元気ですか」 |
| ビジネス | 「立冬を迎え、寒さが一段と厳しくなってまいりました。貴社ますますご隆盛のことと存じます」 |
同じ「11月の挨拶」でも、相手に合わせて言葉を変えることが、ワンランク上の文章につながります。
ポイントは「誰に伝えるか」を意識して言葉を選ぶことです。
11月の挨拶例文バリエーション【上旬・中旬・下旬】
11月といっても、上旬・中旬・下旬で感じられる季節の雰囲気は大きく変わります。
時期に合わせた挨拶を選ぶことで、より自然で心のこもった手紙になります。
ここでは、11月を3つの時期に分けて使いやすい例文をご紹介します。
11月上旬に使える例文
紅葉が色づき始め、秋らしさを楽しむ時期です。
| 例文 | 場面 |
|---|---|
| 「紅葉が美しく染まり始め、散歩が楽しい季節になりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。」 | 友人や家族への便り |
| 「晩秋の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。」 | 改まった挨拶状 |
| 「朝晩が冷え込むようになりました。どうぞご自愛くださいませ。」 | ビジネス文書 |
11月中旬に使える例文
立冬を迎え、秋から冬への移り変わりを意識した表現が多く用いられます。
| 例文 | 場面 |
|---|---|
| 「暦の上では立冬を過ぎましたが、秋の名残を感じる日々が続いています。」 | フォーマルな挨拶 |
| 「山々が冬化粧をはじめ、季節の変わり目を感じますね。」 | 親しい人への便り |
| 「寒さが次第に増しておりますが、皆様にはますますご健勝のことと存じます。」 | ビジネスレター |
11月下旬に使える例文
冬の訪れが間近に迫り、寒さを意識した表現が適しています。
| 例文 | 場面 |
|---|---|
| 「日が短くなり、夜が長く感じられるようになりました。寒さも本格化してまいりましたので、どうぞお身体を大切にお過ごしください。」 | 改まった手紙 |
| 「冬の足音が近づく中、皆様の変わらぬご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。」 | ビジネス挨拶 |
| 「こたつやストーブが恋しい季節になりましたね。どうぞ温かくしてお過ごしください。」 | 親しい人への便り |
時期を意識した挨拶を入れると、形式的になりすぎず、相手に寄り添った文章になります。
11月は季節の変化が大きいため、上旬・中旬・下旬で言葉を使い分けるのがポイントです。
まとめ|11月の手紙は「季節感」と「心遣い」が鍵
11月は秋から冬へと移り変わる季節であり、自然の変化や年末を意識した言葉が手紙に深みを与えます。
手紙の冒頭や結びに季節の挨拶を取り入れることで、形式的な文章に温かみが加わり、相手への思いやりが伝わります。
また、安否を気づかう一言を添えると、さらに丁寧で心のこもった手紙になります。
| ポイント | 効果 |
|---|---|
| 11月らしい季語や慣用句を取り入れる | 手紙に季節感を出し、印象を豊かにする |
| 相手に合わせて挨拶を使い分ける | 改まった手紙からカジュアルな便りまで幅広く対応できる |
| フルバージョン例文を活用する | 安心して書き出せるため、失礼のない手紙が完成する |
特に11月は寒暖差が大きく、体調を崩しやすい季節です。
「ご自愛ください」「お体を大切に」などの一文を忘れず添えることで、心のこもった手紙になります。
ここで紹介した表現や例文を組み合わせ、自分らしい言葉を加えれば、11月の手紙はより温かみのあるものとなるでしょう。